
フリーランスエンジニアに役立つ情報をお届けするフリーランスジョブ編集部です。
近年、SaaS企業が開発の意思決定や設計の工夫、運用のリアルを「テックブログ」として公開する動きが広がっています。そこには、マルチテナント設計やゼロダウンタイム移行、SREの運用自動化、データ基盤の整備、そして生成AIやLLMOpsの実装まで、現場で磨かれた一次情報が詰まっています。
本記事では、2025年時点で注目すべきSaaS企業のテックブログを厳選してご紹介します。日々の課題に直結する実装Tipsから、障害対応や品質改善のプロセス、アーキテクチャ刷新の舞台裏まで、学びをすぐ実務へつなげやすい内容を中心に選びました。
最新機能の導入事例やコスト最適化、パフォーマンス改善に加え、プロダクト組織の働き方や開発文化に触れられるのもSaaSブログの魅力。自分の案件やキャリアに活かせるヒントを、ぜひ見つけてみてください。
※本記事の情報は2025年9月時点の公開内容に基づいています。各ブログの構成や掲載技術、URL等は変更される可能性があります。最新情報は必ず各公式ブログをご確認ください。
目次

画像引用元:RAKUS Developers Blog(https://tech-blog.rakus.co.jp/)
RAKUS Developers Blogでは、実際に開発現場にいるエンジニアやPdM、デザイナーが自らの言葉で開発のリアルを届けています。
たとえば、PRレビューにAIを導入して進行管理を自動化した取り組みや、要件定義の手戻りに直面した新卒エンジニアの試行錯誤など、等身大の経験が綴られているのが魅力です。
さらに「楽楽精算」や「メールディーラー」にAI機能を組み込む開発裏話も紹介されており、SaaSが現場でどう動いているのかを知る手がかりになります。
こうした記事からは、楽楽シリーズ全体に共通する顧客志向の設計思想や改善の積み重ねも伝わってきて、サービスづくりのリアルをより広く学ぶことができます。

画像引用元:Money Forward Developers Blog(https://moneyforward-dev.jp/)
現場エンジニアやSRE、データ基盤、セキュリティのメンバーが等身大で執筆するブログです。障害対応のふりかえりやゼロダウンタイム移行、LLMやエージェントの活用、組織づくりなどテーマは幅広く、図解やコード断片を交えた記事が多いため読み進めやすくなっています。
「マネーフォワード クラウド」を支える設計や品質改善の知見が随所に登場し、サービスの裏側を学べるのも魅力。実運用での検証手順や意思決定の背景も丁寧に紹介されており、「明日自分の環境で試せる」と感じられる具体性があります。
さらに、マイクロサービス間の依存整理やCI/CD改善、大規模DB移行といった規模の大きなSaaSならではの工夫も公開されています。

画像引用元:freee Developers Hub(https://developers.freee.co.jp/)
freee Developers Hubは、現場のエンジニアやSRE、PdMなどが自らの体験を言葉にするブログです。記事はAIエージェントを活用した開発実験や、MySQLの障害事例をふりかえった技術検証、さらには新卒研修での挑戦など幅広いテーマをカバー。
読み手に近い立場の声が多く、不安を抱えやすい駆け出しのエンジニアにとって共感しやすいのが特徴です。特に「freee会計」や「freee人事労務」といったプロダクトを支えるデータ基盤や品質改善の工夫が語られており、SaaSが日常業務にどのように根付いているかを学べます。
図解やコード断片も交えた実務的な記事が多いため、「自分の環境で試してみよう」と思える具体性があります。読後には、開発の舞台裏に触れつつ自分のキャリアを重ねて考えられるはずです。

画像引用元:SmartHR Tech Blog(https://tech.smarthr.jp/)
SmartHR Tech Blogは、エンジニアやPdM、QA、CREなど多様な職種のメンバーが執筆し、日々の実装や組織づくりを等身大で発信しています。社内の工夫だけでなく、外部イベントでの登壇レポートも多く、開発現場の温度感をそのまま届けているのが特徴です。
記事では、Reactのバージョン不一致にどう対応したかや、LLMを活用したテストケース自動生成、CI/CD改善の実践などが紹介されており、規模の大きなSaaS開発で直面するリアルな課題を追体験できます。心理的安全性を軸にしたチーム改善やCRE活動のように、働き方や文化に関する知見も豊富です。
人事・労務クラウド「SmartHR」を支える裏側に触れられるため、機能がどう安定提供されているのかを理解するヒントが得られます。

画像引用元:Sansan Tech Blog(https://buildersbox.corp-sansan.com/)
Sansan Tech Blogは、エンジニアやSRE、R&D、PdM、デザイナーなど多彩な職種が日々の実践を発信する場です。プロダクト改善だけでなく、チーム運営や働き方に関する工夫も交えて語られるため、現場の温度感をそのまま感じ取れるのが魅力です。
記事では、React VirtualizedからReact Virtuosoへの移行判断や、GitHub ActionsにおけるYAML Anchors活用、Elasticsearchインポートを2倍に高速化した手法などが公開されています。
また、AIを用いたJMeterシナリオ生成や、Epoxy削除による技術負債返済の取り組み、契約書DX「Contract One」立ち上げに関する挑戦も共有され、幅広い知見を得られます。

画像引用元:ヌーラボ Tech Blog(https://nulab.com/ja/blog/categories/techblog/)
ヌーラボ Tech Blog は、エンジニアやデザイナー、PdMが日々の開発や検証を綴る場です。自社プロダクトに限らず、個人開発や技術実験のレポートも多く、記事を通して書き手の人柄や試行錯誤が伝わってきます。
記事例としては、個人開発アプリにAWS WAFを導入した話や、RustでBacklog向けのMCPサーバーを作った試み、AIで動画の声をデザインした事例など。さらに「Nulab AI Agent Hackathon」やアクセシビリティレポートのように、組織全体での挑戦や文化を紹介する記事も見られます。
プロジェクト管理ツール「Backlog」などの関連テーマが題材になることもあり、SaaS企業の現場でどう技術が活かされるのかを覗けるのが魅力です。読み進めるうちに、実装のヒントと同時に「チームで工夫しながら働く姿勢」にも触れられるブログです。

画像引用元:サースプラスカンパニー Tech Blog(https://blog.members-saasplus.com/category/tech-blog/)
サースプラスカンパニー Tech Blogは、Salesforceや各種SaaSの導入・運用を支援するメンバーが、実際の取り組みや検証をそのまま発信する場です。現場での体験に根ざした記事が多く、導入の工夫や小さな改善の積み重ねが等身大で描かれています。
記事には、新卒社員がSalesforce認定AIアソシエイト資格に挑戦した合格体験記や、ノーコードでToDoを自動リマインドする仕組みを作った事例、Marketing Cloud Engagementの新機能紹介などが並びます。また、最新のAI機能「Agentforce」や「Einstein」を業務でどう活かすかを考察する記事もあり、読者が自分の業務に照らし合わせやすい内容になっています。
SalesforceやMAツールを実際の業務でどう使うのかに触れることで、単なる製品理解にとどまらず「現場で安心して活かせるイメージ」を描けるのが魅力です。
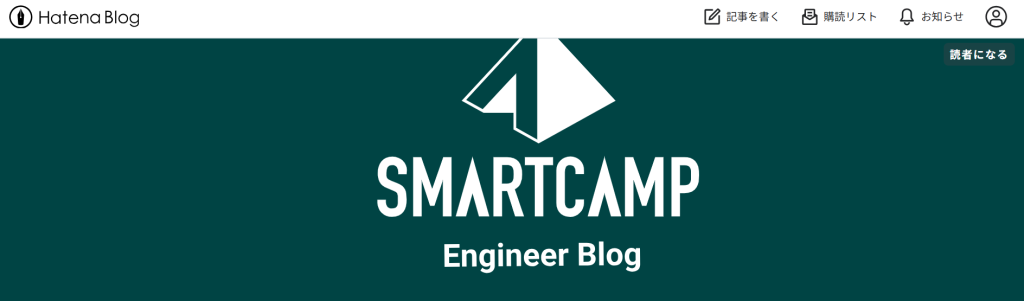
画像引用元:スマートキャンプ Tech Blog(https://tech.smartcamp.co.jp/)
スマートキャンプ Tech Blogは、エンジニアを中心にPdMや新卒メンバーも加わり、それぞれの実践や気づきを言葉にしている場です。技術的な挑戦からキャリアの歩みまで幅広く、現場の体温がそのまま伝わってきます。
記事では、Rails7.1やVue3への移行といったプロダクト改善の裏側、AWS SAMでのSlack bot構築、CircleCIを用いた開発効率化などが公開されています。また「土木工学から新卒エンジニアへ」といった異業種転身ストーリーや、フリーランスから正社員へ至った体験談など、人の歩みを描くエントリも多彩です。
同社が運営するSaaS比較サービス「BOXIL」の文脈と近いテーマも扱われており、SaaSと現場技術のつながりを感じ取れる内容です。サービスづくりを肌で理解するヒントが見つかります。

画像引用元:クラウドワークス エンジニアブログ(https://engineer.crowdworks.jp/)
現場のエンジニアやSRE、EM、新卒メンバーまでが、自分たちの言葉で取り組みを記すブログです。成果だけでなく検証手順や意思決定の背景まで丁寧に触れる記事が多く、初学者でも流れを追いやすい構成になっています。等身大の語り口で、チームの空気感も伝わります。
記事例は、クラウドログ開発チームのAI活用(コーディングエージェントやMCP、KPTでの知見共有、Devinによる不具合一次調査)、フロントエンドのJest→Vitest移行、社内「日報」システムのアーキテクチャ整理、RubyKaigi参加を踏まえたLSPの学びなど、手元に持ち帰りやすいテーマが並びます。
クラウドソーシング「CrowdWorks」や工数管理SaaS「クラウドログ」を支える品質改善・生産性向上の工夫とも結びついており、プロダクト運用のリアルを立体的に理解できます。

画像引用元:Commune Engineer Blog(https://tech.commune.co.jp/)
Commune Engineer Blogは、主にバックエンドやインフラを担当するエンジニアを中心に、機械学習やソフトウェア開発に携わるメンバーが実務で得た知見を記録する場です。記事のトーンはフラットで、日々の開発で直面した課題や工夫をそのまま綴っているのが特徴です。
たとえば「MySQLのメジャーバージョンアップを安全に行うための検証手順」や「GitHub Actions経由でVertex AIへエージェントをデプロイした際の学び」、「TypeScriptデコレータを用いたリファクタリングの工夫」など、現場で役立つノウハウが公開されています。また、言語処理学会への参加レポートなど、技術発表や学術的な取り組みにも触れられています。
同社が提供するコミュニティサクセスプラットフォーム「Commune」を支える技術基盤や開発チームの姿勢が自然と伝わり、実装のヒントだけでなく、開発組織のリアルを学べる場になっています。

画像引用元:kickflow Tech Blog(https://tech.kickflow.co.jp/)
kickflow Tech Blogは、フロントエンドやバックエンドのエンジニア、QA、CREなど多彩な職種のメンバーが執筆し、開発や運用での工夫を等身大の言葉で伝えています。コード実装だけでなく、品質保証やサポートの現場からの知見も加わり、読み進めるうちにチーム全体の温度感が伝わってきます。
記事には「Nuxt4への段階的な移行戦略」「QAチームが取り入れる自動テストやAIツールの活用」「RailsとJavaScriptを統一して使う実装事例」などがあり、実務に役立つヒントが多く紹介されています。さらに、非エンジニアがAIを用いてヘルプデスクやQAポータルを構築した記録もあり、キャリア初期の方にとっても身近に感じやすい内容です。
同社が提供するワークフローSaaS「kickflow」を支える技術や文化の一端に触れられる内容で、サービスづくりの裏側を知るきっかけになります。

画像引用元:エキサイト TechBlog(https://tech.excite.co.jp/)
エキサイト TechBlogは、現場で活躍するWebエンジニアや新人エンジニア、さらにはインターン生までが日々の学びを綴るブログです。業務での実装工夫からキャリア初期の気づきまで幅広く、現場の空気感がそのまま伝わる記事が多いのが特徴です。
具体的には、長年稼働していたPHP5系からSpring Boot 3 / Java21へと移行した「エキサイトブログ」トップページのリプレイス記録や、Vue2からReactへの移行に挑んだエンジニアのTips紹介、さらにインターンがReact移行や広告制作に携わった体験談など、多様なテーマが並びます。
移行戦略やインフラ構成の工夫など、実務に直結する知見も多く公開されており、同社が展開する事業管理プラットフォーム「KUROTEN」やウェビナー支援サービス「FanGrowth」といった事業に共通する、“サービスを長く育てる視点”も感じられます。

画像引用元:ANDPAD Tech Blog(https://tech.andpad.co.jp/)
ANDPAD Tech Blogは、現場のエンジニアやSRE、データアナリストなどが、自分たちの取り組みを率直に記す場です。記事は開発や運用の実務に直結するテーマが多く、プロダクトを支える裏側を身近に感じられるのが特徴です。
たとえば、GitHub CopilotのAgent modeをDataformに適用してチーム内に普及させた試みや、SREと開発者が連携してインフラコストを削減した実例、ML API基盤でのMLOpsの取り組みなどが公開されています。
同社が提供する建設・施工管理SaaS「ANDPAD」を支える技術基盤や開発文化が自然と伝わり、日々の開発に役立つヒントやサービスづくりのリアルを学べる内容です。

画像引用元:hacomono TECH BLOG(https://techblog.hacomono.jp/)
hacomono TECH BLOGは、SREやバックエンドエンジニア、UXエンジニア、QAなど多彩な職種のメンバーが執筆し、日々の工夫や学びを共有する場です。実装ノウハウに加え、社内イベントやキャリア初期の経験記録などもあり、開発チームの雰囲気が身近に伝わってきます。
記事は「MySQLの集計処理が遅くなった原因を調査した記録」や「Goでエラーハンドリングライブラリを自作した話」、「モジュラーモノリス導入の経過報告」など実務的な内容が中心です。さらに、QAエンジニアがPlaywrightでE2Eテストを実装した体験や、UXエンジニアの役割紹介など、キャリア初期の方にも参考になる記事もそろっています。
同社が提供する会員・決済SaaS「hacomono」を裏で支える技術や文化が紹介されており、読者はサービス開発の実際を具体的に知る手がかりを得られます。

画像引用元:Goals Tech Blog(https://zenn.dev/p/goals_techblog)
Goals Tech Blogは、エンジニアが日々の試行錯誤や学びをそのまま言葉にして届ける場です。バックエンドやフロントエンドの実装だけでなく、データ分析やインフラ運用まで幅広いテーマが扱われており、同社が展開する飲食店向けオペレーションSaaS「HANZO」を支える基盤づくりや改善の姿勢が随所に感じられます。
記事例としては、「回帰モデルや状態空間モデルを用いた需要予測の実践」「フロント初心者によるReact開発の学び」「GitHub ActionsでTerraform基盤を共通化した取り組み」などがあり、現場での工夫が丁寧に共有されています。
さらに、音声認識アプリの制作やAWS勉強会のレポートといったテーマも並び、技術をどのように現場で活かしているのかが具体的に伝わってきます。

画像引用元:TAIANテックブログ(https://zenn.dev/p/taian)
TAIANテックブログは、エンジニアを中心にPdMやQAといった多彩なメンバーが執筆するブログです。記事のスタイルは「試してみた」や「振り返ってみた」といった幅広さがあり、実装ノウハウにとどまらず、チームで働く等身大の空気感も伝わってきます。
実際には「React Router v6の高速化に挑んだ取り組み」「AWS CloudWatch Logs Insightsを用いたログ調査」「PlaywrightとCypressの比較レポート」など、現場で役立つテーマが多く並びます。
さらに「スクラム導入でチームがどう変化したか」「スタートアップでのQA立ち上げ記録」といった組織づくりのエピソードもあり、キャリア初期の方にも共感しやすい内容です。こうした日々の改善や挑戦の積み重ねが、ブライダル業界向けVertical SaaS「TAIAN」を支える土台となっています。
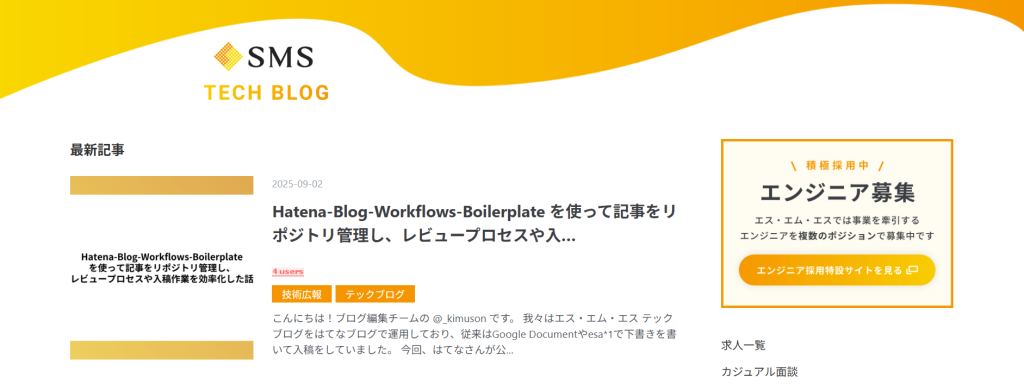
画像引用元:エス・エム・エス エンジニア テックブログ(https://tech.bm-sms.co.jp/)
エス・エム・エス エンジニア テックブログは、エンジニアをはじめ、PdMやデータサイエンティスト、人事など多彩な職種のメンバーが執筆する場です。内容は実装ノウハウにとどまらず、組織づくりや働き方にも広がっており、読み進めるうちに現場の息づかいが自然と伝わってきます。
具体的には「Hatena-Blog-Workflows-Boilerplateを使った記事管理の事例」「Datadogによるモニタリングの実践」「プロダクト開発エンジニアの目標設定の考え方」など、日々の実務に直結するテーマが紹介されています。
さらに、開発生産性カンファレンスの登壇レポートや、データサイエンティストのキャリアストーリーといった記事もあり、等身大の学びに触れられるのが特徴です。主力サービス「カイポケ」「リハプラン」など福祉・介護領域を支えるSaaSの技術的裏側や組織文化も、ブログ記事を通じて理解できます。

画像引用元:PLEX Product Team Blog(https://product.plex.co.jp/)
現場のエンジニアやPdMが、自分たちの開発体験を日々の言葉で記しているのが「PLEX Product Team Blog」。技術スタックや開発フローのまとめにとどまらず、ジュニア勉強会やチーム内の取り組みまで紹介されており、少人数ならではの柔軟さやスピード感が感じ取れます。
たとえば「サクミルチームの技術スタックと開発フロー」では、TypeScriptやRuby on Railsを軸にした開発環境に加え、CopilotやChatGPTといったAIツールの導入事例も公開。さらに、Adapterパターンを題材にした勉強会やSlackでのナレッジ共有の場が取り上げられており、現場の空気が伝わってくるようです。
同社が展開する建設業向けSaaS「サクミル」や人材プラットフォーム「プレックスジョブ」と地続きの知見が並びます。
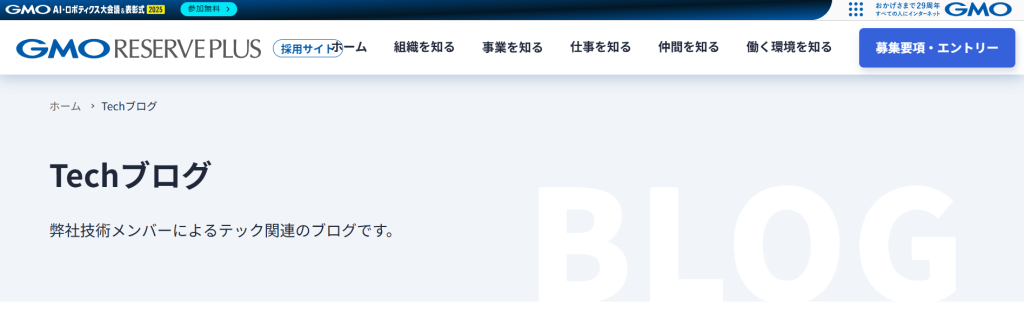
画像引用元:GMOリザーブプラス Techブログ(https://gmo-reserve.plus/recruit/blog/)
GMOリザーブプラスの技術メンバー自身が記事を書き留めているのが「GMOリザーブプラス Techブログ」です。たとえば、Chrome DevToolsのパフォーマンスパネルを使ったデバッグの手法が丁寧にまとめられていて、実務ですぐ役立つ内容だと実感できます。
また「エンジニアブログのエコシステムをつくりました【microCMS】」という記事では、microCMSとAstro、GitHub Actionsを組み合わせて、記事の更新が自動で反映される仕組みをどう作ったかが、開発背景からつぶさに共有されています。
さらに、「リザーブプラス AIハッカソン開催だ! テーマはAIエージェント!」や「SaaSを22本構築したエンジニアの話」といったキャリア系の投稿もあり、単なる技術解説にとどまらない幅広い視点が得られる構成です。
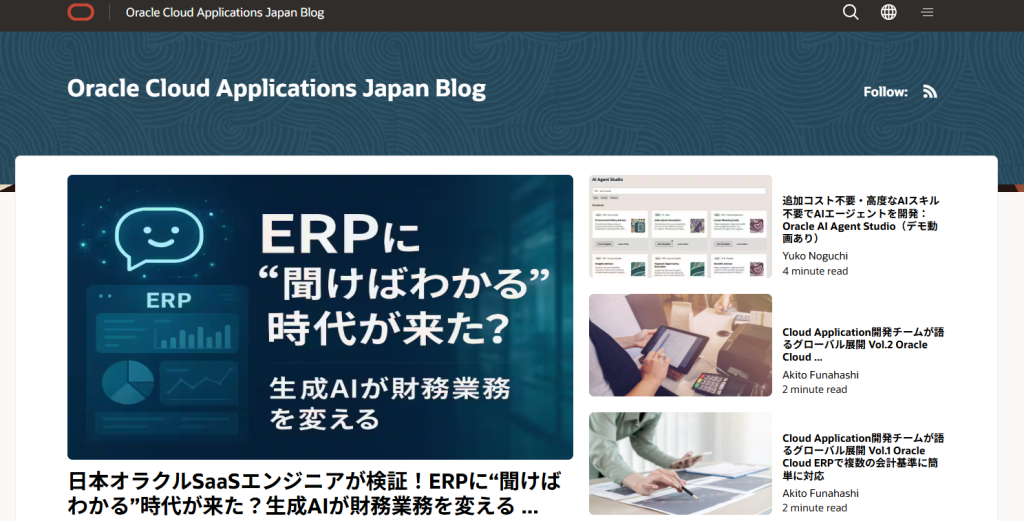
画像引用元:Oracle Cloud Applications Japan Blog(https://blogs.oracle.com/saas-jp/)
日本オラクルの SaaS エンジニアや開発チームが執筆する「Oracle Cloud Applications Japan Blog」は、先進的な業務課題に寄り添った記事が並んでいます。
たとえば「ERPに“聞けばわかる”時代が来た?」では、生成AIを使って財務業務にどう変化が起きるかが検証されています 。また「追加コスト不要・高度な AI スキル不要で AI エージェントを開発:Oracle AI Agent Studio(デモ動画あり)」では、Fusion Applications 向けの AI エージェントを手軽に構築できる仕組みが紹介されています 。
同社が提供する「Oracle Fusion Cloud Applications(ERP/HCM/CX)」は、多様な業務を支える基幹システムの集合です。ブログ記事を通じて、そうした基盤がどのように検証され、進化しているのかが伝わってきます。
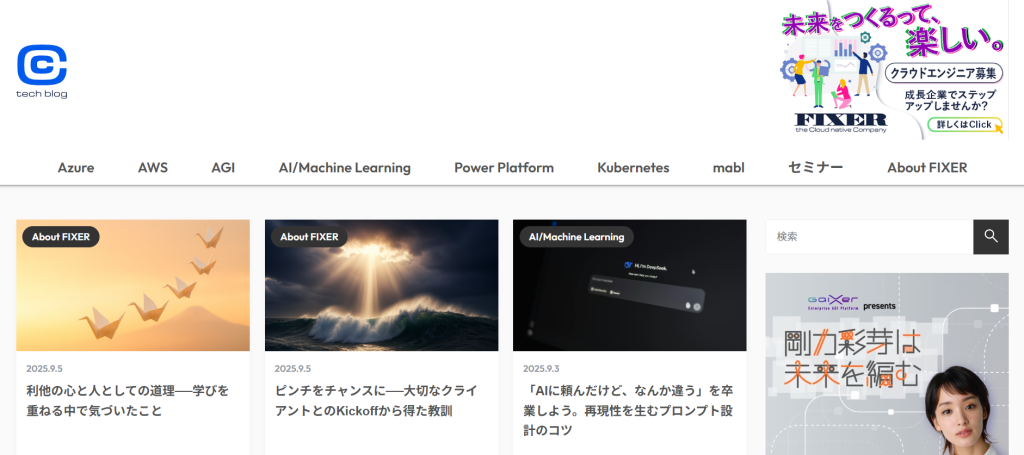
画像引用元:cloud.config Tech Blog(https://tech-blog.cloud-config.jp)
エンジニアや広報担当者が現場での学びや気づきをそのまま紡いでいるのが「cloud.config Tech Blog」です。トーンはほどよく肩の力が抜けており、AzureやAI、Playwrightなどの技術的な実践体験からキャリアの歩みまで、多彩な内容が並んでいます。
たとえば「『AIに頼んだけど、なんか違う』を卒業しよう。再現性を生むプロンプト設計のコツ」では、生成AIでありがちな「なんか違う…」を超えていくためのプロンプト設計のヒントが具体的に紹介されています。また「Playwrightで自動テストを実装したときの話を書くぞ~~~」では、Web UIテストの自動化を実務でどう組み立てたか、そのリアルな体験が伝わってきます。
Azureなどのクラウド基盤運用を支える「cloud.config」サービスの裏側と直結しており、技術選定の理由やチームとしての試行錯誤が素直に綴られています。

画像引用元:OPTiM TECH BLOG(https://tech-blog.optim.co.jp/)
エンジニアやデザイナーが自分たちの実践をそのまま言葉にしているのが「OPTiM TECH BLOG」です。記事はAIやクラウド活用の技術検証から、社内イベントの企画レポート、デザイン組織の取り組みまで幅広く、現場での試行錯誤や工夫が率直に綴られています。
たとえば「AIに頼んだけど、なんか違うを卒業しよう」では、生成AIを活かすためのプロンプト設計の工夫が具体的に解説されており、駆け出しのエンジニアにもヒントが得やすい内容です。
また「エンジニアが全社横断のイベントを企画から運営までやってみた」では、AI体験会を通じた学びの共有が描かれ、技術とコミュニティ形成の両方を感じ取ることができます。
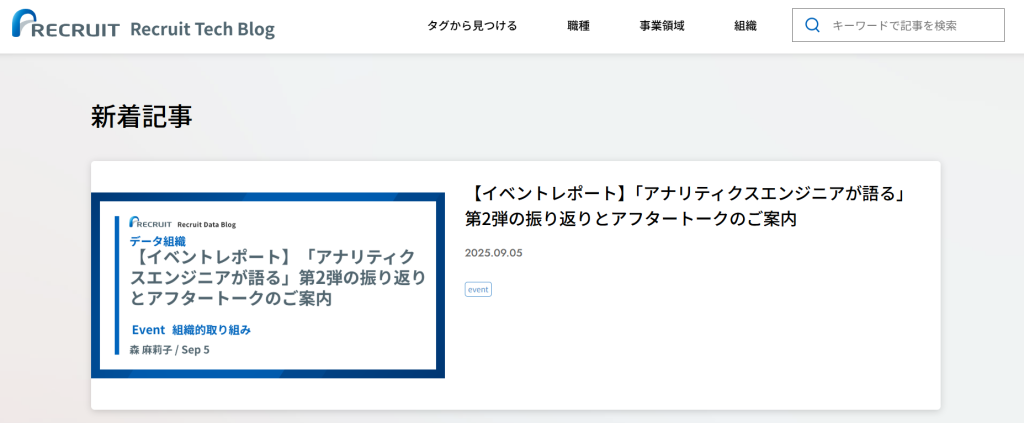
画像引用元:Recruit Tech Blog(https://techblog.recruit.co.jp/)
エンジニアやデザイナー、データ推進室のメンバーまで幅広い職種が登場するのが「Recruit Tech Blog」です。新人研修の内容公開や、デザイン大量修正を支えた仕組みづくりなど、現場の試行錯誤を率直に言葉にしており、働き方や開発のリアルがそのまま伝わってきます。
記事の幅はとても広く、たとえば「RecSys Challenge 2025 で優勝しました」では推薦システム分野の世界的コンペでの挑戦が紹介され、「分散型と集中型の両輪アプローチで実現するクラウドコスト最適化」では内製基盤 Crois を用いた FinOps 実践が語られています。
同社が展開する「Air ビジネスツール群」や「リクナビ」「スタディサプリ」など多様なサービスは、こうした知見の積み重ねから支えられています。

画像引用元:CARTA TECH BLOG(https://techblog.cartaholdings.co.jp/)
エンジニア、Customer Reliability Engineer(CRE)、デザイナーといった幅広い職種が発信しているのが「CARTA TECH BLOG」です。自作PCの排熱問題に向き合うコラムから、fluctのテクニカルサポートを支えるチームへのインタビューまで、軽やかな語り口で現場の学びや工夫が伝わります。
記事の具体例としては、「Fetch API (Blink) のソースコードを眺めてみる」や「.NET MAUI HybridWebViewで作る!リアルタイム商品ピックアップアプリ開発記」など、最新技術の探索や実装の記録が手にとるように紹介されています。
ブログからは、サービスの裏側に息づく知恵や視点が自然に伝わり、自分の学びやつながりを生むきっかけにもなりそうです。

画像引用元:とことんDevOps(https://devops-blog.virtualtech.jp/)
エンジニアが日々の実践や検証をそのまま記録しているのが「とことんDevOps」です。日本仮想化技術のメンバーが執筆し、クラウド運用やCI/CD、IaC、コンテナ開発といったテーマを中心に、業務現場で役立つ知見がわかりやすい言葉で共有されています。
たとえば「Apple SiliconなMacでVagrantを使ってテスト環境を用意する」では最新環境への適応過程が紹介され、「以前書いたDockerのマニフェストをARM Macでも動くようにGitHub Copilotを使って修正する」ではAIツールを取り入れた実践例が語られています。
また、月刊VS Code通信や月刊DevOpsニュースの連載では、アップデート情報や業界トピックを定期的に整理し、初学者でも流れをつかみやすい内容になっています。同社はDevOpsやクラウド運用に特化したプロフェッショナルサービスを提供しており、ブログに蓄積される試行錯誤はサービスの現場と直結しています。
今回取り上げたSaaS企業のテックブログには、設計判断の背景や移行時のつまずき、SREの運用自動化、データ基盤の整備、そして生成AIやLLMOpsの実装まで、現場で磨かれた一次情報が丁寧に記されています。
成功談だけでなく検証過程や意思決定の根拠、計測指標まで開かれている記事が多く、学びを自分の案件へ置き換えやすいのが魅力です。継続して追うことで、設計の引き出しやデバッグの勘所が少しずつ増えていくのではないでしょうか。
※本記事の情報は2025年9月時点の公開内容に基づいています。各ブログの構成や掲載技術、URL等は変更される可能性があります。最新情報は必ず各公式ブログをご確認ください。